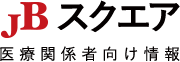自己免疫疾患にまつわる知識・情報UPDATE
Vol.6 自己免疫疾患研究のトレンドと今後の研究発展への期待
女性と自己免疫疾患
これまでに紹介した自己免疫疾患の特徴からもわかるように、自己免疫疾患は全体的な傾向として女性に多い(図1)1)-5)。一部、男性に多い疾患もあるが、自己抗体が出現する疾患は圧倒的に女性が多く、自己免疫疾患患者の約7割は女性といわれている6)。
 <参考>
<参考>日本内分泌学会. 一般の皆様へ. 内分泌の病気. 甲状腺. https://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=7(2024年9月閲覧).
難病情報センター. 指定難病一覧. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5461(2024年9月閲覧).
Nakajima A, et al. Int J Rheum Dis. 2020; 23: 1676-1684.
吉良潤一ほか.第5回多発性硬化症・視神経脊髄炎全国臨床疫学調査結果第2報.厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 神経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準・重症度分類・ガイドラインの妥当性と患者 QOL の検証. 令和 2年度 総括・分担研究報告書. 2021; 29-31.
Aotsuka Y, et al. Neurology. 2024; 102: e209130.
男性より女性に多い理由として、X染色体の関与やエストロゲンなど性ホルモンの影響、抗体産生量の多さをはじめとする免疫応答の高さなどが示唆されているが7)、明確な答えは得られていない。ただ、全身性エリテマトーデス(SLE)では、女性に多く発現しているToll様受容体(TLR)7が病態形成に関わっているとされており8)、この分野の研究が数多く行われている。
TLRは病原体特有の分子(構成成分、RNA、DNAなど)の特徴を感知する「パターン認識受容体(PRR)」の一種である。マクロファージや樹状細胞などの細胞表面や細胞内小胞(エンドソーム)に存在し、外部から侵入した病原体を認識すると、免疫応答を引き起こす。ヒトではこれまでに10種類ほどのTLRが確認されており、それぞれ存在する場所や認識する物質が異なる。TLR7はX染色体上にあって、エンドソーム内でウイルスのRNAを認識する。
SLEでは炎症性サイトカインであるI型インターフェロン(IFN)αの過剰産生が起こっていることが知られている。SLE患者の血液検体を用いてINFαの産生経路を調べる研究を行ったところ、形質細胞様樹状細胞(pDC)ではTLR7を刺激することでINFαの産生が亢進することが判明した(図2左)9)10)。さらに別の経路として、単球では小胞体でウイルスのDNAを認識するstimulator
of interferon genes (STING)を介したINFαの産生亢進が認められた(図2右)10)11)。
これまでにSLE患者ではTLR7遺伝子の変異が同定されたという報告もあり12)、こうした研究結果を基に新たな治療薬の開発も進められている。
SLEは妊娠・出産後に発症することがあり、SLE患者では妊娠中に症状が増悪するケースもある。挙児を希望する場合や妊娠中の治療管理などきめ細かなケアが必要であり、出産・育児と仕事を両立する女性が増えたいま、さらなる病態解明や新規治療薬の開発が待ち望まれる。
 <参考>
<参考>Murayama G, et a. Arthritis Res Ther. 2017; 19: 234.
Murayama G, et al. Rheumatology (Oxford). 2020; 59: 2992-3002.
久我大雅, 三宅幸子. 実験医学 増刊. 2022; 40: 2499-2504.
加齢と自己免疫疾患
かつて自己免疫疾患は免疫能が盛んな若い人の病気と考えられており、年齢とともに免疫機能が低下すれば症状は軽減すると思われていた。ところが、最近は関節リウマチ(RA)などのように高齢発症の自己免疫疾患患者が増えている。
高齢者ではT細胞の成熟の場となる胸腺の退縮やT細胞の老化、B細胞の減少による抗体の産生低下に加え、自然免疫系の細胞も貪食能や抗原提示能が低下する13)。こうした加齢に伴う免疫機能の低下は「免疫老化(immunosenescence)」と呼ばれ、感染症やがんの発症リスクにつながると考えられている。この免疫老化に関わる重要な要素として、近年、高い関心が寄せられているのが「加齢に伴う炎症(inflammaging)」14)である。老化の特徴をまとめた欧州の最新の知見では、老化に関わる新たな要素として「慢性炎症」が追加され、免疫機能との関連についても言及されている(図3)15)16)。
細胞は老化してもすぐに死滅するわけではなく、老化細胞として長期にわたり体内に蓄積する。それらが炎症性サイトカインや免疫細胞を誘導するケモカインなどさまざま因子を分泌し17)-19)、がんをはじめとする加齢性疾患の発症や病態の悪化につながる可能性があると考えられている20)21)。
加齢に伴い増加することで知られている加齢関連B細胞(Age-Associated B
cells:ABCs)は、自己免疫疾患モデルでも確認されている22)23)。さらに最近の研究では、SLE患者やRA患者の末梢血で加齢に伴って増加する加齢関連ヘルパーT
(ThA)細胞が同定されたことも報告された24)。この細胞は抗体産生を誘導する作用と細胞傷害を活性化する作用の2つの働きをあわせ持つという。これらの研究結果から、自己免疫疾患のように免疫が過剰に活性化された病態では、ABCsやThAのように老化でみられるような細胞が増えている可能性があると考えられる。
今後、このような研究が蓄積されれば、高齢者と若年者の自己免疫疾患に違いがあるかどうかがみえてくるかもしれない。
 López-Otín C, et al. Cell. 2023; 186: 243-278.およびLópez-Otín C, et al. Cell. 2013; 153: 1194-1217.より作成
López-Otín C, et al. Cell. 2023; 186: 243-278.およびLópez-Otín C, et al. Cell. 2013; 153: 1194-1217.より作成
細胞解析技術の発展と今後の免疫研究への期待
さまざまな細胞の存在や機能が見出されるようになった背景には、この数十年で細胞解析技術が大きく発展してきたことがある。かつて、細胞の遺伝子解析はDNA断片を1つずつ手動で解析していたが、技術の自動化と高速化が進み、今では一度に数百万もの遺伝子の発現状況を網羅的に解析できるようになった。しかも、シングルセル解析と呼ばれる技術が実用化されたことで、細胞を集団(バルク)としてではなく、一つずつ個別に処理できるようになり、個々の細胞での遺伝子やたんぱく質の発現状況の違いなど、細胞の多様性や不均一性が観察できるようになった(図4)25)。
細胞の不均一性は治療抵抗性の一因と考えられており、こうした新しい研究手法を用いて、自己免疫疾患の領域でも治療反応性や予後によって疾患を層別化する試みが進められている。
 <参考>
<参考>Guruprasad P et al. J Exp Med. 2021; 218: e20201574.
解析技術の発展に加え、最近では解析対象となる細胞も広がりをみせている。自己免疫疾患の領域では、免疫細胞だけでなく、組織の細胞を解析する試みが増えている。たとえば、RA患者の滑膜組織を用いた解析26)などがその例であり、目下、滑膜細胞に関して多くの研究が行われている。
ヒトの細胞は37兆2,000個あるといわれており、現在、この全細胞の種類の同定とマッピングを目的とした国際プロジェクト“Human Cell Atlas(HCA)”が進行中である27)。2024年9月現在、日本を含めた99ヵ国が参加して免疫を含む18の領域でデータの生成が進められている。自己免疫疾患はもちろん、あらゆる疾患の病態解明や新たな治療法の開発に向け、研究者と臨床家のたゆまぬ努力が続いている。
おわりに
副腎皮質ステロイドが開発される以前、自己免疫疾患は苦しみの中で死を待つことを余儀なくさせられる疾患であった。免疫の異常はがんのように病巣を取り除くというわけにはいかず、いまでも根治はかなわないが、治療選択肢が大きく広がったことで、長く付き合っていくことのできる疾患となった。治療選択肢が増えれば、診断する意義も高まる。だからこそ、できるだけ早く診断し、治療を始めることが患者の未来を支えることにつながる。
免疫は「内なる宇宙」とも称されるくらい奥深く、人知を超えたしくみで生体のバランスを維持している。まだ明らかになっていないことは多いが、それ故に新たな知見が次々と見出されている領域である。自己免疫疾患の診療に携わる医師だけでなく、より多くの医療従事者に免疫に興味を持っていただき、常に知識をアップデートしながら医療の最前線に臨んでいただければ望外の喜びである。
- 日本内分泌学会. 一般の皆様へ. https://www.j-endo.jp/modules/patient/index.php?content_id=1(2024年9月閲覧).
- 難病情報センター. 指定難病一覧. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5461(2024年9月閲覧).
- Nakajima A, et al. Int J Rheum Dis. 2020; 23: 1676-1684.
- 吉良潤一ほか.第5回多発性硬化症・視神経脊髄炎全国臨床疫学調査結果第2報.厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 神経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準・重症度分類・ガイドラインの妥当性と患者 QOL の検証. 令和 2年度 総括・分担研究報告書. 2021; 29-31.
- Aotsuka Y, et al. Neurology. 2024; 102: e209130.
- Hayter SM & Cook MC. Autoimmun Rev. 2012; 11: 754-765.
- Ngo ST, et al. Front Neuroendocrinol. 2014; 35: 347-369.
- Souyris M, et al. Sci Immunol. 2018; 3: eaap8855.
- Murayama G, et al. Arthritis Res Ther. 2017; 19: 234.
- 久我大雅, 三宅幸子. 実験医学 増刊. 2022; 40: 2499-2504.
- Murayama G, et al. Rheumatology (Oxford). 2020; 59: 2992-3002.
- Vinuesa CG, et al. Nat Rev Nephrol. 2023; 19: 558-572.
- 山下政克 編. 基礎から学ぶ免疫学. 羊土社, 2023年11月.
- Franceschi C & Campisi J. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2014; 69 Suppl 1: S4-9.
- López-Otín C, et al. Cell. 2023; 186: 243-278.
- López-Otín C, et al. Cell. 2013; 153: 1194-1217.
- Acosta JC, et al. Cell. 2008; 133: 1006-1018.
- Kuilman T, et al. 2008; 133: 1019-1031.
- Coppé JP, et al. PLoS Biol. 2008; 6: 2853-2868.
- Chan ASL, et al. Genes Dev. 2019; 33: 127-143.
- Ikegami K, et al. Aging (Albany NY). 2023; 15: 1279-1305.
- Hao Y, et al. Blood. 2011; 118: 1294-1304.
- Rubtsov AV, et al. Blood. 2011; 118: 1305-1315.
- Goto M, et al. Sci Immunol. 2024; 9: eadk1643.
- Guruprasad P, et al. J Exp Med. 2021; 218: e20201574.
- Mizoguchi F, et al. Nat Commun. 2018; 9: 789.
- HUMAN CELL ATLAS. https://www.humancellatlas.org/(2024年9月閲覧)