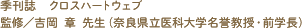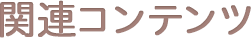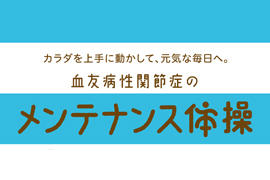第25回 大地震被災と出血症・血栓症
本誌監修の吉岡章先生が専門医(家)にインタビューし、一つのテーマを深く掘り下げる「クローズアップ・ハート」。第25回は、能登半島地震でJMAT(日本医師会災害医療チーム)の一人として現地に駆け付け、避難している人たちのケアに当たった金沢大学附属病院の朝倉英策先生に、避難生活を送る上での健康維持、特に血栓症の予防や対策についてうかがいました。どのように気を付け、どのように備えておけばいいでしょうか。

血液内科
病院臨床教授
朝倉 英策先生
- ●1984年 金沢大学医学部 第三内科入局
- ●1998年 金沢大学附属病院 高密度無菌治療部 准教授
- ●2014年 金沢大学附属病院 病院臨床教授
- ●日本血栓止血学会 監事・認定医 日本検査血液学会 理事 日本血液学会評議員・専門医 ほか
- ●YouTube「血栓止血のお役立ち情報」配信中

〒920-8641
石川県金沢市宝町13-1
TEL:076-265-2000(代表)
URL:https://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/
被災時・避難生活で起こる数々の深刻な疾患
吉岡先生先生は地震当日、どのような経験をされましたか?
朝倉先生お正月でしたので、金沢市内の自宅でくつろいでいました。金沢は震度5強でしたが、私の経験した中で最大の揺れでした。能登では震度7あったといいます。テレビでは大津波警報が出て、アナウンサーが必死に避難を呼びかけていました。
吉岡先生たいへんなご経験でしたね。大地震や大災害の際には、どのような外傷や内科的疾患が考えられますか?
朝倉先生けがは程度の差もさまざまで、多数あったと思います。急性期は外科系の対処が重要になってきます。その中でも最重症の一つがクラッシュシンドローム(挫滅症候群)。がれきの下敷きなどで横紋筋が挫滅、融解状態になって、救助され解放された時にカリウムやミオグロビンが多量に出て不整脈や腎障害を引き起こすものです。あとはストレスからくる急性冠動脈症候群なども突然死を引き起こします。血圧が上昇し、不整脈や脳卒中も増えたようです。あまりニュースにはなっていませんが、こうしたことで命を落とされた人も一定数おられたと思います。
吉岡先生エコノミークラス症候群も話題になりましたね。
朝倉先生車中泊がよくないことは、新潟県中越地震の時から皆さんよくわかっていたのですが、私が現地に行った時も、少数ではあるものの危険を承知のうえで車中泊をされていました。ペットを飼っているとか、女性の方は避難所のプライバシーの問題などで車中泊を選ぶ方が少数いらっしゃいました。
吉岡先生ほかに地震後時間がたってから起こってくる健康被害もありますか?
朝倉先生寒い時期でしたので、新型コロナウイルスやノロウイルスなどの感染症が広まってしまった避難所もありました。断水が続き衛生状態が保てないことも大きな悪影響となりました。
吉岡先生避難が長くなると精神的な問題も生じますね。余震も続いていたでしょうし。
朝倉先生そうですね。皆さん気丈にふるまわれていたようですが、よく話をきいてみると、家のことが心配で眠れないという方も多くいらっしゃいました。
あなどれないエコノミークラス症候群。
JMAT対策チームの活動で早期発見へ
吉岡先生エコノミークラス症候群について少し詳しくお話しいただけますか。
朝倉先生あまり動かずに臥床を続けるなどで下肢の血流が悪くなり、深部の静脈に血栓ができて、再び歩くなどした時に血流に乗ってその血栓が肺まで飛び、肺血栓塞栓症を起こすという、命にも関わるものです。飛行機のエコノミークラスの狭い座席に長時間座っていることで起こるということで語源になりましたが、実際にはファーストクラスでも起きます。正式には静脈血栓塞栓症と言いますが、患者さんには伝わりにくいので、通りのいいエコノミークラス症候群と言うことも多いです。上肢に血栓ができる場合もありますが、9割以上は下肢に生じます。
吉岡先生それには何か、自覚症状がありますか?
朝倉先生それがほとんどないのが怖いところです。両脚が腫れているのでそうではないかとおっしゃる方もいらっしゃいますが、そのほとんどは単なるむくみです。この病気で腫れるときは片脚だけというのも特徴です。ただし、全く症状がない人の方がはるかに多いです。静脈瘤と混同されている方もいらっしゃいますが、大きく違います。突然死の直前まで症状がないというのは、心筋梗塞や脳梗塞など、全ての血栓性の疾患に共通です。
吉岡先生ではもう、検査をするしかないのですね?金沢大学JMATエコノミークラス症候群対策チームとしてはどのような活動をされたのでしょうか。
朝倉先生チームは例えば医師1名、看護師1名、臨床検査技師が2名、ロジ*1名などからなり、臨床検査技師が血栓形成の可能性を示す血中Dダイマーをまず測定します。非常にコンパクトな測定機器があって、私たちはそれを2台持っていきました。10分で結果が出るので、2台で1人当たり5分換算。それで正常値が出た人の99%は大丈夫ですので、数値が高かった人だけエコーで血栓を探しました。エコーもコンパクトな機器があって、ただ少し時間がかかるので全員は無理です。Dダイマーとエコーの機器は、非常に重要なアイテムでした。
※被災地などで医療活動を円滑に行うための後方支援吉岡先生血栓が見つかった方はどのくらいいらっしゃいましたか。
朝倉先生比較的広い、大規模な避難所で1割程度、何人かで身を寄せ合ってというような小規模なところですと2割くらいいらっしゃいました。このまま放置すると危ないという方もいらっしゃいました。
吉岡先生そんなにですか。地震から時間がたっても起こるのですか。また、血栓ができてから肺に飛ぶまでの時間の余裕はありますか。
朝倉先生おそらく1週間後くらいから出始めて、2~3カ月はリスクが続くという感じです。血栓が肺に飛ぶまでの時間はもうさまざまです。
吉岡先生血栓ができる方の年齢層などはありますか?
朝倉先生もともと高齢者の多い地域でしたけれど、血栓が見つかる方が必ずしもご高齢かというとそうでもありません。
エコノミークラス症候群予防の3つのポイント
吉岡先生地震などに被災して避難生活を送る際、静脈血栓塞栓症を予防する方法はありますか。
朝倉先生お話ししましたように自覚症状がほとんどないので予防が大切です。予防のポイントは3つあります。
1.よく動くこと
歩ける方は歩き、歩けない方でもベッドの上で足首を動かす「底背屈運動」をすることで予防できます。自分でできない方でも、介助の方の手を借りるだけでも違います。
2.脱水予防
能登半島地震では長い間断水が続きましたが、ペットボトルの飲料水は早い段階で届いていました。むしろ、断水のためもあってなるべくトイレを使いたくないと、飲水を控える人もおられたのが問題でした。
3.弾性ストッキングの着用
これはかなり効果があり、避難所にも届いて皆さん持っていました。ただ、履き方が難しくて着用していないという人が多かったのが残念です。手でかかと部分を引き出して履くとけっこう簡単に履くことができます。私は普段から着用していますが、講義など立ちっぱなしの時も疲れが激減します。足首からきちんと圧をかけてくれるものがよく、ふくらはぎの上部を締め付けるものは血流をさまたげて逆効果の時もあります。外国製のものはサイズが合わない場合もあります。私は日中身に着けて、就寝時は血流も重力に逆らわなくていいのでぬぐようにしています。稀にですが、できている血栓の状態とか持病などで着用を控えたほうがいい方もいらっしゃいますので、医師に相談するといいでしょう。車中泊は避けてほしいのですが、いざという時に備えて車内に弾性ストッキングを用意しておくよう、学生さんへの講義では言っています。
吉岡先生ほかに、こういう薬がいいというものはありますか。
朝倉先生責任を持って処方できる医師がいて薬局が機能していることが大前提ですが、DOAC(直接経口抗凝固薬)は便利だと思います。避難所でも服用しやすく飲んだその日から効果が表れます。ただ飲み忘れると効果がなくなります。
いざという時のために薬の備えを
吉岡先生血友病などの出血性疾患をもっている人は、震災などの時に備えて、どのようなことに気をつけたらいいですか。
朝倉先生血友病に限らず、薬を常用しなくてはならない方は、万が一に備えて常日頃から2~3週間分の薬を持っていると安心です。お薬手帳を薬局に出せば医師の処方箋なしで薬をもらえるという緊急処置も取られましたので、お薬手帳は財布や保険証同様、貴重品として携帯しておくことをお薦めします。旅行の場合なども同様です。最近アプリもありますが、非常時はネットの接続が困難になることも多いというのも頭に入れておいてください。
吉岡先生個人の備えに加えて、緊急時の医師の活動や薬の供給体制を引き続き考える必要がありますね。
(2025年Vol.78)
審J2502309