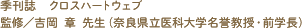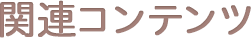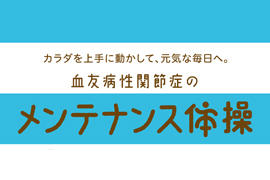鹿児島大学病院輸血・細胞治療部(小児科) 助教 中村 達郎先生
中核病院で自身の経験を生かし
先生が血友病の診療に携わるようになったきっかけと時期を教えてください。
中村先生私自身に血友病Aの重症があります。小さな頃は出血時補充や予備的補充しかなく、昼夜を問わず病院通いが欠かせませんでした。ですから医療者を志した時から自分の経験を生かして血友病を診る小児科医になろうと決めていました。研修医の頃からその思いを話していたので、血友病初学者向けのイベントなどに声をかけていただきました。その後鹿児島市立病院で血友病の診療を学び、2022年に血友病診療連携地域中核病院が市立病院から当院に移った時に、10名ほどの患者さんとともにこちらに移って診療を続けています。これまで入院の血液腫瘍患児の診療などと並行して血友病の診療を行っていましたが、昨年4月から輸血細胞治療部に移り、血液凝固を専門とする小児科医として、より血友病の診療に注力できるようになりました。
鹿児島大学病院の血友病の診療状況はいかがですか。
中村先生現在、小児科の血友病外来は基本的には私が診療していますが、10代までの小児の範囲で血友病Aの方がおよそ10名、血友病Bの方が2名ほどいらっしゃいます。インヒビターがある方はいらっしゃいません。
患者さんはどのような地域から通院されていますか。
中村先生8割方は車で1時間以内の地域ですが、残りの方は2時間ほどかけて通院してもらっています。
鹿児島大学病院の血友病の診療の特徴はいかがですか。
中村先生私は初診の時に私自身が血友病であるということを患者さんに伝えています。血友病患者が行う血友病外来っていうのがいちばんの特徴かと思います。自分の伸びない関節やレントゲン写真を見せ、こうならないように定期補充をがんばろうという話をすることもあります。血友病患者の子どもたちにとって、いい見本ではなくとも、こうならないような治療が必要ということが目で見てわかるのはいい環境かなと思います。関節エコーや自己注射なども私自身が慣れていることなので、患者さんの身になって指導ができます。
他科との連携についてはいかがですか。
中村先生保因者妊婦の分娩で産科と、また関節評価で整形外科とやり取りをしていますが、頻繁に関わることのない科では、担当者が定まっていなく対応が一時的な部分がありました。そこで昨年、血友病の院内連携チームを立ち上げました。薬剤部、リハビリテーション科、看護師などに核になる担当者をつくって連携を強めていく取り組みをしているところです。また臨床検査科の橋口照人先生にも、熱心に相談に乗ってもらっています。
県内外の地域病院やクリニックとの連携はいかがですか。
中村先生鹿児島市外の患者さんで定期補充の注射がまだできないお子さんは、地域の小児科でしていただき、処方と評価はこちらで行っています。地域によっては、多くの患者さんの定期補充の静脈注射を引き受けてくださっている病院もあります。鹿児島県には離島もありますが、当院で製剤やその投与スケジュールを立てて現地の医療機関に依頼し、やり取りしながらある程度現地で完結するように診療をしたこともあります。県外では、多くの先生方と繋がりができ、研究に参加して、鹿児島から遺伝子検査の検体を出せる体制をつくっています。他にも色々な研究会などに声をかけていただき、血友病の最新情報を日々アップデートするようにしております。
患者に寄り添い生涯にわたる診療を
自己注射等の指導についてはどのようにされていますか。
中村先生開始時期の目安は10歳以降と考えていますが、自己注射ができないと通院の負担があり、旅先で注射を打てる病院を探して紹介状を持っていく必要も出てきます。自己注射技術を獲得していればだいたい2~3カ月に1度の受診ですみますので、希望があれば小学校低学年から指導を始めることもあります。最初は注射器に触ってもらうなど少しずつ注射に対する恐怖を取り除き、ステップを踏んで指導をしていきます。また自分がどういう病気で何のために注射を打たなくてはならないかよくわかっていない子も多いので、注射指導とともに病気の知識を伝えるようにしています。
製剤の選択はどのようにされていますか。
中村先生血友病Aの場合、中学で運動部に所属しているなど活動度の高いお子さんには週3回のSHL(半減期標準型製剤)を中心に、そうでなければ週2回のEHL(半減期延長型製剤)をベースに考えています。医学的な効果のほかに、困りごとや不安など患者さんやご家族の思いをききながら、無理強いはしないよう薬の選択をするようにしています。新薬が出た場合も、情報提供はきちんとしながら相談しています。
血友病診療のスタッフの育成についてはどうお考えですか。
中村先生あまり患者数が多い病気ではなく、医療者が出会う機会も少ない病気なので、特に専任の医師の育成には至っていません。ただ県内全体に患者さんがいて、乳幼児期から生涯にわたって多診療科の連携が必要になるので、さまざまな科の先生たちに知っていてほしい病気です。専門家をたくさん増やすより、多くの科の先生に血友病の最低限の知識を理解していただくことが必要です。そのためにも血友病患者さんに触れる機会を少しずつ増やしていく工夫を、県内全体でやっていきたいと思っています。その中で興味をもってくれる人がいればこの領域に入ってきていただきたいですね。私自身は血友病の診療がしたくて医者になったのですが、自分で終わりにならないよう、継続できる診療体制を作っていくのが目標です。院内連携を立ち上げて以降、興味をもってくれるスタッフも少しずつ増えてきています。
鹿児島県に患者会はありますか。
中村先生私が子どもの頃にはありましたが、その後立ち消えになってしまいました。ですが、他県にいた時に参加した患者会で、さまざまな患者さんのお考えに触れ、悩んでいるのは自分だけじゃないと思えたのは大きな収穫でした。そこで2017年から私が主催して患者会を開くようにしています。小児から60代以上まで15名ほどの方に参加していただいています。子どもたちにとってみれば、これからの自分を想像する、成人にとっては自分の経験を子どもたちにアドバイスする、いい機会となる交流の場です。さまざまな形で今後も続けていきたいと思っています。
保因者診断についてはどうお考えですか。
中村先生通院をしている患者さんのご家族から、自分の凝固因子活性が知りたいという相談を受けることはあります。遺伝子検査までいかなくても、ご自分のこれからの出血リスクに備えるため、万が一の時の対応を知るための情報として、凝固因子活性を測るということはご希望に沿って行っています。また、私自身が血友病患者であることを話すと、保因者妊婦の分娩の際も、意外と病気があっても普通に社会で仕事ができるのだと安心してくださる方もいます。
今後どのような診療体制を目指していきたいですか。
中村先生院内では院内連携チームを、県外とは血友病の専門医療機関との連携を、さらに強め継続していきたいですね。また鹿児島県内に散在している成人患者さんの診療連携を進めていきたいと考えています。普段は地域の病院で診療され、年に一度ほど当院で関節の評価や適切な医療方針の提案などを行えるようにしていけたらと考えています。
(2025年3月記)
審J2504038
輸血・細胞治療部(小児科) 助教 中村 達郎先生


〒890-8520
鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1
TEL:099-275-5111(代表)
https://www.hosp.kagoshima-u.ac.jp/
中村先生ご自身が血友病患者であることを開示した上で、診療を実施されています。自らの経験を交えつつ、医師・患者さんの二つの目線からの診療はユニークでフレンドリーですね。小児期から成人・高齢者まで、患者人生に寄り添って診ていただけるのは心強いですね。