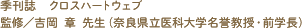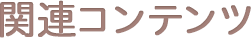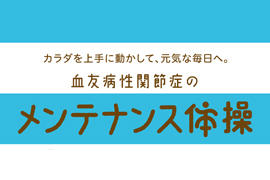大学病院に犬がいること~聖マリアンナ医科大学病院における動物介在療法の紹介~
「こんにちは、勤務犬です。」ベッドサイドのピッタリと閉ざされたカーテンを開ける瞬間、一瞬の緊張が走るが、その後私たちを迎え入れてくれる患者さんはいつも優しい笑顔である。
一瞬にして患者を笑顔にする、医療従事者にはなかなかできないことをいとも簡単にしてしまう勤務犬の実力に私はいつも尊敬の念を抱く。
聖マリアンナ医科大学病院では、医師の指示のもと重い病と闘う患者およびその家族に情緒的安定や闘病意欲の向上を促進させることを目的として、2015年4月に勤務犬による動物介在療法(Animal Assisted Therapy;AAT)を導入した。
AATとは医療従事者が個々の患者にあった補助療法として動物を選択し、治療計画の中に動物の介在により期待される変化を組み入れた治療ゴールを設定し、その変化を観察及び記録していくことと定義される。
現在は3代目勤務犬のハクが、看護師と兼務をしているハンドラー2名の同伴のもと、週2回のAATを行っている。
当院は我が国で初めてAATを導入した大学病院であるが、AAT導入には長い準備期間を要した。AATの導入は2012年に入院中の白血病の少女が「犬に会いたい」と活動団体に手紙を書いたことに始まる。
それをきっかけにAATを導入したいと考える同僚医師や看護師らと共に活動を開始した。まずはAATの周知や病院に犬がいることに慣れてもらうために社会福祉法人日本介助犬協会と公益社団法人日本盲導犬協会の協力を得て動物介在活動を延べ53病棟で行い、講演会の開催やポスター掲示なども行い、啓蒙活動を徹底した。
犬とハンドラーの育成に関しては日本介助犬協会の協力を得て、資金面では同窓会への援助の申請と募金口座の開設を、安全面に対しては感染制御部と連携し、署名活動、マニュアル作成、AATの依頼書や患者への説明同意文書の作成、入院のしおりへの記載などを行い、約3年の準備期間を経て、ようやく2014年に勤務犬導入部会が発足、2015年に当院でのAAT導入が実現したのである。
2015年4月~2023年5月の期間、初代勤務犬ミカと2代目勤務犬モリスにより、421人の患者さんに対して2021回のAATを行った。対象疾患は悪性腫瘍が最も多く、次いで変性疾患、脳血管障害、切迫早産など多岐にわたり、全ての診療科、全ての病棟でAATを実践してきた。
AATの目的としては大きくリハビリテーション、緩和ケア、疾患の受容と適応の促進、手術や検査支援の4つに分類される。リハビリテーションでは「自分の足で歩いて勤務犬と一緒に桜を見に行く」「麻痺側の腕のリハビリも頑張って一眼レフのカメラを抱えて勤務犬の写真を撮る」など、患者自らが立てた目標をスタッフと共有することで、勤務犬が来ない日のリハビリテーションにも自然と力が入り、セルフケア能力を促進させる効果があった。AATの効果として96.2%の症例で看護目標を達成でき、フェイススケールの検討ではAATの前後で有意な改善が認められた。
現在、客観的な評価を行うべく、AAT前後で質問紙法と、唾液中のストレスマーカーを測定する研究を行っている。
この数年間で勤務犬が起こす人間には成し得ない多くの奇跡をたくさん見てきた。
神経の病気で体が動かないにも関わらず勤務犬を触ろうと必死で手を伸ばした患者さん、勤務犬を見ようと動かない首をなんとか動かそうと努力する患者さん、交通事故で片足を切断し布団から出てこなかった青年が自分の意志でベッドから立ち上がったこと、手術が怖くて泣きながら入室するのに1時間かかっていた先天性疾患の小児がリードを持ち笑顔で自らの足で手術室に入室したこと、骨髄移植中の白血病の小児が吐きながらも窓越しに最高の笑顔をみせてくれたこと、死にたいと言ってナースコールが頻回だったがんの末期の患者さんが勤務犬と会うために化粧をはじめたことなど、勤務犬は患者さんたち一人ひとりに本来の人格を取り戻させ、病気に立ち向かう勇気と、他人を思いやる優しさ、自分が必要とされている自己肯定感を与えてくれる。
どんなに辛く先が見えない入院生活でも、残り少ない人生であっても、楽しみや生きがいを持つことの大切さを勤務犬は教えてくれる。
さらに、勤務犬がいると患者さんだけでなく、ご家族、そして医療スタッフも自然に笑顔になる。AATは患者を取り巻く環境に精神的な安らぎを与え、医療スタッフと患者や家族を結びつける有用な手段ともなる。勤務犬の周りにはいつもたくさんの笑顔があふれ、病院とは思えない温かく優しい空気が流れる。
みんな笑顔で笑い合えること、当たり前のようで病院ではなかなかできないことを勤務犬は実現してくれる。犬が普通に廊下を歩く病院、すれ違うスタッフがみんな笑顔で犬に挨拶してくれる病院、この風景がずっとずっと続くことを願ってやまない。
患者さん一人ひとり、疾患や背景が異なり、それぞれ抱えている悩みや不安、克服すべき課題は異なるが、個々の患者の問題点を抽出後、具体的な治療計画の中に動物介在により期待される変化を組み入れた治療ゴールを設定することで、医療の一環としてAATを行うことができている。
今後も患者さんの体のみならず、心も大切にする医療、愛ある医療を実践していきたい。
(2025年Vol.78)
審J2502309