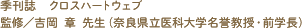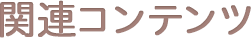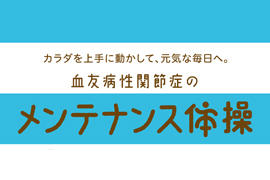患者さんの“ライフパートナー”として
~ 一生涯を共に歩む看護のかたち ~
患者さんの一生に関わるということ
血友病の患者さんは生涯にわたって病気と付き合っていく必要があります。現在は、“出血ゼロを目指す時代”になったとはいえ、出血や痛みに対する不安、将来への悩みなど、目に見えない苦しさを抱えている方も少なくありません。
そうした思いを安心して表出できる関わりが大切だと感じています。看護師として、医療の提供者であると同時に、人生に寄り添う“ライフパートナー”のような存在でありたいと願っています。ある講演会で患者さんが、『看護師には“ライフパートナー”のような存在でいてもらいたい』と語られた言葉が強く心に残り、自分の看護を振り返るきっかけとなりました。
血友病看護は、必要な処置を行うだけではなく、『人生に寄り添う』ことの大切さを感じています。
ライフステージに応じた看護ケア
血友病患者さんのケアは、年齢や生活背景によって変化します。小児期には、病気を理解できるように対象に合わせた説明や、ご家族へのサポートが必要です。病院を“いやなことをする場”ではなく、“頑張っていることを認め、身体を守ってくれる場”と感じてもらえるように努めています。
思春期には自立への支援を行い、成人期以降は社会や家庭の中での生活を支えるサポートが求められます。さらに、治療の進歩により高齢期を迎える患者さんが増えています。高齢化に伴い、関節変形による日常生活動作の制限や通院困難、視力低下による自己注射の困難さ、認知機能低下や生活習慣病の合併による服薬管理の複雑化など、多くの課題が生じます。当院では、血友病診療チームが定期的にカンファレンスを行い、必要な方には早期から介入し、地域と連携して在宅生活を支えています。
ライフステージに応じた看護ケアを通して、“その人らしい生活”を守ることを大切にしています。
患者さんが“その人らしく”いられるように
血友病看護に携わって4年、私は技術的な支援だけでなく、患者さんが話したいときに耳を傾け、困ったときにはすぐに寄り添える距離にいたいと心がけています。診察室には可能な限り同席し、診察前後に声をかけることで、診療に直接関係のない話からもケアのヒントを得られることがあります。
例えば、検査が追加になった患者さんが「また病院に来ることになった。難儀やわ~。」と話されたことから、不安を事前に把握し、医師に止血管理の調整をすることができました。また、面談で将来の生活の場が話題になった際、ご両親から「一緒に住めるのもいつまでかわからない」との言葉を受け、医療ソーシャルワーカーと連携して在宅支援を整えたこともありました。
ご家族からは、「そんなことまでしてもらえるの?」と驚かれましたが、地域で安心して生活できるよう支えることも医療者の大切な役割だと考えています。こうした日々の関わりの中で、患者さんの不安や苦痛を少しでも軽減し、“その人らしさ”を守ることが、私のやりがいにつながっています。
これからの血友病看護のかたち
治療は進化していますが、人と人とのつながりは変わりません。長く病気と向き合ってこられたその人生に敬意をもって関わり、患者さんが「病気を忘れられる時間」を増やせる存在でありたいと思っています。新薬の登場で治療の選択肢は広がっていますが、その選択を患者さんの生活にどう合わせるか、生活の質をいかに維持・向上させるかは、看護師が多角的な視点で支えていくことが重要だと感じています。
今後も多職種との連携を強化し、SDM(Shared Decision Making)※を活かして一人ひとりの患者さんに向き合い、安心と希望を届けられるよう“ライフパートナー”としての看護を磨き続けたいと思います。
※SDM:血友病のケアと治療について患者と医療チームが協力して決定するプロセス(WFHより引用)
(2025年Vol.80)
審J2510187