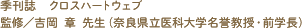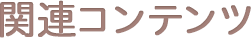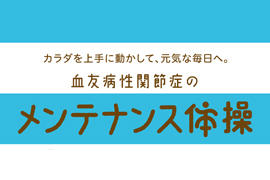長崎大学病院小児科 助教 舩越 康智先生
交通が不便だからこその地域連携
先生が血友病の診療に携わるようになったきっかけと時期を教えてください。
舩越先生卒業して長崎大学病院の小児科の医局に入り、研修医として血液グループの診療に関わっていましたが、白血病などの小児がんが主でした。1年ほど長崎市立市民病院での勤務を経て大学病院に戻り、本格的に小児血液の診療に関わりましたが、血友病患者さんと関わる機会はほとんどありませんでした。その後2011年から外来に出て少しずつ血友病の患者さんに触れるようになり、2018年に上司が退職して血友病の患者さんを引き継ぐことになりました。その後現在に至るまで、新しい治療方法や薬剤などが次々登場し、治療のバリエーションが増えた変遷を見てきました。
長崎大学病院の血友病の診療状況はいかがですか。
舩越先生小児科で私が診ているのは、血友病Aの患者さんが18名、Bの患者さんが1名です。Aのうち軽症が2名、中等症が8名、重症が8名、Bの方は中等症です。血液内科でも診ているので、患者さんはもっといらっしゃると思います。インヒビター保有の方は小児科にはいらっしゃいません。
長崎県全体の診療状況はいかがですか。
舩越先生佐世保市総合医療センターに小児血液外来があり当院のスタッフが診察に行っていますが、そこに8名の患者さん(A6名、B2名)がいらっしゃいます。長崎県は立地が複雑なため交通が不便で離島も多く、血友病に限らず診療状況はよくありませんが、離島に住んでいる血友病の方は現在1名のみです。当院と佐世保の小児科では、専門医が対応しています。
院内での血友病診療の体制はどのようなものですか。
舩越先生小児科では血液外来の対応をしています。患者さんの数が多いわけではないので「血友病外来」ではなく他の血液疾患の外来患者さんに対応しながら血友病の外来も行っています。3名で外来を分担し、患者さんが通院しやすい曜日に合わせている状況ですが、血友病の患者さんの大半が私の担当の曜日に来られている状況です。
他科との連携はいかがですか。
舩越先生近年で一番変わったことは整形外科との関わりです。関節症の人はほとんどいませんが、関節エコーも積極的に使いながらしっかり関節を診ていこうという最近の診療の流れに乗って、年に1回程度の関節チェックを患者さんに勧めています。整形外科の定期外来に血友病患者さんを紹介するようになり、徐々に併診患者さんが増えています。この機会に将来的には、リハビリテーションも組み合わせていけたらと思っています。また当院は小児歯科がしっかりしているので、早い時期から歯科に入ってもらうことも多いです。
地域の病院やクリニックとの連携はどうなっていますか。
舩越先生長崎県は湾をぐるっと囲むような形をし、また離島も多いので、こちらに通うのが困難な地域もあります。前任者の時代から、基本的に地元にかかりつけ医をもって、日常的な診療や血液凝固第Ⅷ因子製剤の処方などはそちらでしていただき、半年に1度くらいこちらに来て処方や治療方針の確認・見直しをするという仕組みを作っていました。特に乳幼児期、まだ家庭注射ができていない頃は地域の先生方にお世話になっています。近くに開業医がいない場合は二次病院などにお願いし、地域との連携は早くからとれています。近年はノンファクター製剤で治療をする方が増えてきて通院頻度が減ったり、静脈注射の患者さん自体も減ったりしていますので、今後はまた関わり方が変わってくるのかなとは思っています。
血友病診療のスタッフ育成はどのようにされていますか。
舩越先生医師の入れ替わりはありますが、若手の血液専門の医師は、やはり小児がんから勉強をスタートすることが 多く、患者さんの数も少ないため血友病にはほとんど関わることがないのが現状です。ただ、血友病は製薬会社による勉強会の機会が多いので、そういうものに参加し、患者を受け持ちながら関わることを増やしていけたらと思っています。新薬も多いのでついていくには勉強もどんどんしないとなりません。
自己注射の指導はどのようにされていますか。
舩越先生凝固因子製剤の場合は、導入は1歳前後、なるべく2歳までに地域の病院での週1~2回程度の定期補充で開始し、だんだん回数を増やしていくようにしていました。目安として3、4歳くらいまでには保護者の方が打てるように、小学校高学年から中学に入る前後に自己注射に切り替えるという一般的な形です。外来でシミュレーターのようなもので練習します。以前は福岡県北九州市の産業医大の1週間の入院指導プログラムを利用する患者さんもいましたが、コロナ禍の影響で県外への移動ができなくなって以来中断しています。
患者さんの人生を狭めない診療を
製剤の選択はどうされていますか。
舩越先生自己注射なら週に2回か3回は打てますが、長崎県の患者さんは通院の難しさや地域の先生方の負担もあるため、注射回数を減らしたいという傾向があります。半減期延長型の製剤ができた際、すぐに導入をしたところも多く、私もずいぶん早くに導入しました。ノンファクター製剤が登場して出血しにくくなりましたが、活動性の高い患者さんにはやはり凝固因子製剤が有効であったりするので、私は患者さん一人一人の希望や活動度、活動の頻度、アクセスなどに応じて、ご本人や家族、そして医療従事者の負担が少ないように製剤を選んでいます。病気や治療によって患者さんの人生を狭めないよう「患者さんのやりたいことができるように治療を選択する」というのが最も大事だと思っています。
保因者診断や保因者健診についてはどうお考えですか。
舩越先生保因者のほとんどは無症状で、自覚していない方が多いという問題があります。また患者さん当人も一般の 方々も、医療者でさえも、女性は血友病とは関係ないと思っている人が多いので、そこの啓発が大事だと思っています。出産時に新生児に問題が起きたり、ご自身の貧血がひどかったりします。生まれてきた子が女児だった場合、保因者である可能性があるので、遺伝形式を知っておくことは必要だと思われます。血液凝固第Ⅷ因子活性が極端に低い女性もいて、ここ数年は、保因者ではなく女性血友病と呼びましょうという流れになってきています。女の子だから関係ないという考え方は危険です。ただ、遺伝的な問題は難しく、本人に保因者であると伝えるタイミングもあり、知らない権利もあります。また、無症状の未成年者の遺伝子検査を本人の理解なしにはするべきではないと考えています。当院では、疑いのある方は同意が得られれば凝固因子活性を確認し、低めの方はときどき来院してもらって、それなりの年齢になったら本人にもお話しするという形が多くなっています。保因者の凝固因子活性値の幅はかなり広く、遺伝子検査までしないと確定はできないのが実情です。
フォン・ヴィレブランド病など、血友病以外の先天性血液凝固異常症の患者さんもいらっしゃいますか。
舩越先生はい。何人かいらっしゃって、なんだか血が止まらない、ということで検査して判明しています。幸い適切な製剤投与でほとんど出血せず成長していますが、調べたらもっといると思います。ほかにもトロンボモジュリンの異常や先天性アンチトロンビン欠乏症などの患者さんもいらっしゃいます。
今後目指していきたい診療体制はどのようなものでしょうか。
舩越先生血友病外来を立ち上げるほど患者さんは多くないのですが、もっと包括外来的な診療を充実させてより質の高い診療を提供したいと考えています。地域の先生方を含めた勉強会なども開きたいのですが、患者さんの数が少ないので、なかなか集まらないと思われます。一方、院内では、研究会とか製薬会社の勉強会などに血液内科と声を掛け合って参加することも増え、連携の機運も高まっています。やがては院内で血友病勉強会を開いたり症例カンファレンスなどを行うようになればいいと思います。
(2025年8月記)
審J2510187
小児科 助教 舩越 康智先生


〒852-8501
長崎県長崎市坂本1-7-1
TEL:095-819-7200(代表)
https://www.mh.nagasaki-u.ac.jp/
長崎県の医療圏は海岸線が長く、離島も多くて複雑ですが、血友病医療連携は長崎大学病院と佐世保市総合医療センターを中心にうまく行われています。舩越先生の「患者さんのやりたいことができる治療環境を整えたい」とのご方針は素敵ですね。