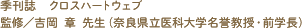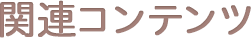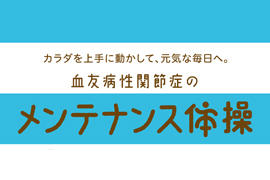第27回 血友病性関節症について
本誌監修の吉岡章先生が専門医(家)にインタビューし、一つのテーマを深く掘り下げる「クローズアップ・ハート」。第27回は、血友病性関節症について、敦賀医療センターリハビリテーション科の竹谷英之先生にうかがいます。血友病患者さんの関節症の状況や痛み、治療法や予防などについて話していただきました。

リハビリテーション科
医長
竹谷 英之先生
- ●1997年1月 国立療養所福井病院 整形外科 医長
- ●2003年7月 国立福井病院 リハビリテーション科 医長
- ●2005年2月 東京医科大学 医学博士
- ●2006年4月 東京大学医科学研究所附属病院 関節外科 講師・科長
- ●2023年4月 独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター リハビリテーション科 医長

〒914-0195
福井県敦賀市桜ケ丘町33-1
TEL:0770-25-1600
URL:https://tsuruga.hosp.go.jp/
吉岡先生先生が血友病性関節症に深く関わるようになったきっかけは何ですか。
竹谷先生福井の大学を卒業して6年ほどたった時に、国立福井病院(現:敦賀医療センター)に赴任しましたが、そこは昔から血友病患者さんを診てきた病院でした。そこの先生方の下で、手術と止血管理を教わり、患者会や製薬企業から呼ばれて講演などをするうちに、血友病を診ている全国の先生方とのつながりができていきました。国立福井病院は当時から全国の血友病の患者さんが来られる病院でしたが、その中のおひとりの先生とのつながりで東京に呼ばれ、退官後また戻って今に至ります。
出血のために関節の機能や形が変化
吉岡先生血友病性関節症とは、どのようなものですか。
竹谷先生一言で言うのは難しいのですが、血友病の患者さんが関節の中に出血を起こして、それを起点として関節内の環境が変化し、最終的に関節の機能や形態を変化させた状態ということになります。主観的に「痛い」かどうかではなく、あくまで画像上変化が認められるものということになります。
吉岡先生血友病患者さんの中で、関節症による痛みを感じている方は多いですか?
その程度や発生しやすい部位などについて教えてください。
竹谷先生実は「痛み」というのは主観的なもので、整形外科医にとって最も客観的に表現しにくい症状なのです。人によって感じ方が違い、違和感をもっていても「痛み」と感じない人もいます。Aさんの痛みとBさんの痛みとを比較することはできないわけですね。ですから、血友病性関節症も、画像での変化を定義としているわけです。部位に関しては、私が関わった頃には膝が最も多かったのですが、ここ15年くらいは足首が多くなっています。
吉岡先生では、血友病の重症度によって、関節症の重症度や痛みに変化はありますか。
竹谷先生血友病の重症度は「出血しやすさ」ではなく因子活性値で区別されますので、まれですが重症でも関節症がない方もいれば、軽症でも関節症が重い方もいらっしゃいます。それでも因子活性の低い重症の方の方が出血しやすいので、関節症の率は高くなりますが、重症ほど頻繁に痛み、軽症は痛みの頻度が低い、というようなことはなかなか言えません。
吉岡先生これも個人差があるということですね。
止血管理をしっかりし、筋力をつける
吉岡先生血友病の関節の疼痛を軽減するためにどのような対策や治療を行っていますか?
重症度や年代によって治療は異なりますか。
竹谷先生関節痛の一番の原因は出血ですので、出血をさせないというのが治療の原点です。ただ、止血管理は整形外科的な治療ではありません。小児の場合、止血管理が行われたうえで出血させにくい体をつくるとなると、筋骨格系の発達が重要になります。つまりは、ぶつけても出血しないくらいの止血治療をしていただいて自由に遊ばせる、それが整形外科的な対策になります。血友病だからとご両親が運動を控えさせ、そのために関節には画像上何の問題もないのに筋力がないというお子さんもいます。整形外科的な治療の目的のひとつは、健やかに育つようにするということだと考えます。一番簡単で難しい治療なのかもしれません。
吉岡先生子どもが自由に動き、運動するということを、血友病ではない子どもと同程度にはしないと、逆に出血しやすくなったり、いざという時の障害度が重くなるということですね。
竹谷先生私の感覚ですが、思春期の、成長が止まるくらいまで関節症がなく育った方は、その後も関節の出血があまりみられない傾向があります。決してゼロではないのですが。ですから、それまでの止血管理をしっかりとしていただき、適度な運動で筋骨格系をしっかり作っていくことが大切だと思います。
吉岡先生血友病患者さんの関節痛がQOL※に及ぼす影響について、教えてください。
※ Quality of life(生命や生活の質)竹谷先生QOLっていうのはなかなか難しい言葉で、時には私がその患者さんになってほしい生活と、ご本人が望む生活との間に差があることもあります。
吉岡先生それぞれの基準があって、第三者として簡単に言うことはできないということですね。
竹谷先生その方にとっての生活の質が担保されれば満足なわけなので、そのへんを考慮することも大切です。
吉岡先生サポーターや装具は進歩していますか。それにより生活がしやすくなったということはありますか。
竹谷先生材質がよくなったり軽くなったりということはありますけれど、大きくは変わっていません。リハビリをする時にロボットを装着し、補助されて立って歩く感覚を身につける器具のようなものは発達してきていますが、日常使いではないですね。それにサポーターや装具は、はずすことを前提に使うものです。それを使い続けることを前提に生活するようになってはいけないと思います。
関節の様子をセルフチェック
吉岡先生血友病患者さんが関節痛を起こさないように、日常的にしたほうがいいことはありますか。
竹谷先生私は、血友病の診察をした患者さんにはほぼ「毎日関節の動きを確認してください」と言っています。出血していてもしていなくても、今日は肘がここまで伸びる、ここまで曲がる、こうすると痛いなどを実感していただき、痛みなどが続いたり変化があったりしたら気にしてほしいと思います。私たちも一緒で、気が付けば体が硬くなっていたと感じることがありますが、関節症のある方はその進行が速いので、日常的な身体機能をご自身でチェック・評価することが大切です。また、日常使う筋肉は意外と限られているので、動ける方は、ラジオ体操でもいいので全身運動をして筋肉を落とさないようにしていただきたいですね。「ここの筋肉をつけたい」という目的のある体操だけではなく、バランスのいい運動も必要です。
治療から予防へ
吉岡先生血友病の治療環境はこの数年で大きく変化しましたが、それに伴い患者さんの関節症の発症頻度や治療法などに変化を感じていらっしゃいますか。特に幼少時から凝固因子製剤の定期補充療法やノンファクター製剤を使用している患者さんの関節出血の状況などに違いは出てきていますか。
竹谷先生それはまだはっきりとはわかりませんが、ノンファクター製剤はほぼ体重に応じて処方し、効果が一定程度あるので、地域や医師による治療の格差がなくなってきたように感じます。今まで痛がっているからリハビリを控えていたような患者さんも、してみようかという状況になる。そういう意味では大きな進歩です。医師も患者も家族も、出血の恐怖から、精神的に救われ、前向きな治療ができるようになってきている気がします。ただ、医者も患者さんも、それを過信して気を緩めるのはよくありません。
吉岡先生今後の血友病患者さんの整形外科的な治療やリハビリテーションについて、方向性や展望を聞かせてください。
竹谷先生これは難しいのですが、大きくとらえれば、今までは「治療」であって、これからは「予防」、つまり関節症にさせない、機能低下を起こさせないというふうに変わっていくべきと思います。将来的には、整形外科医は、膝が悪い子、足が悪い人としてその患者さんを診て、血友病「だから」という認識を持たずに治療できる時代が来るといいなと思いますね。
吉岡先生そういうことが、ご本人にもご家族にも、治療者にも自然に思えるようになるといいということですね。
(2025年Vol.80)
審J2510187